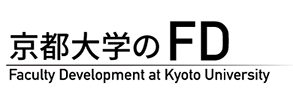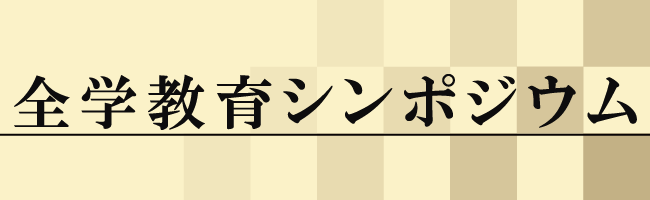- ホーム ->
- 主催 ->
- 新任教員教育セミナー(2014.9.25開催) ->
- テーマ5「研究室運営」
新任教員教育セミナー(2014.9.25開催)
テーマ5「研究室運営」
|
|
グループ5は「研究室運営」ということで、宮野先生に学際総合教育研究推進センターの事例紹介を受けて、ディスカッションを行いました。私は国際高等教育院の金丸と申します。 この新任教員教育セミナーは、先ほどの前半のグループもそうですが、どちらかというと学生全体の教育ということで、教育FDに関するお話が多かったのですが、ここのグループでは研究室ということで、宮野先生のお言葉を借りるとラボラトリーディベロプメント(LD)という新しい言葉を頂き、研究室が、これからの大学の中では非常に大事だというお話がありました。そもそも大学には研究・教育・社会貢献という三つの大きな役割があるのですが、これを担っているのは実は研究室で、大学の実質を担っているという意味で、われわれがいる研究室が非常に大事だということで、ここがこれからの大学の中で大きく変わっていかなければ、大学も変わっていかないというお話でした。 研究室運営がなぜ大事かというと、今までは、カリスマだったり、力もお金も持っていた教授がぐいぐい引っ張っていくというような研究室が多かったのですが、これからは、時代も変わってきて、それでは学生もついていかないし、研究室の運営もうまくいかない。研究室自体が担っている役割も、研究をぐいぐいやっていくことももちろん大事なのですが、それだけではなくて研究室を通じて学生をどうやって育てていくか、人材をどうやって育てていくかというところが非常に大事である。研究室に求められる役割として、研究室はこれから「育人」というキーワードでやっていかなければいけないということでした。 研究室として成果を上げていくためにこれからどういうふうにやっていくかということでは、今までは行動で、実験をさせたり研究をさせたりして、結果の質、成果を上げていくというやり方だったわけですが、実際はその裏側にある、実際の行動、結果を変えるために、どういうふうに研究室がやっていくかというときに、その裏には、なぜそのようなことをやるのか、そして、それをやるためにはどういう人間関係をつくっていかなければならないのかというような、行動と結果の関係の裏側にある関係と思考、人間関係と研究に対する思考を変えていかなければいけないというお話がありました。そして、関係を変えるためには、コミュニケーションをしっかり行っていかなければいけないのですが、何のためにコミュニケーションをするのか。研究室には、学生、教授など、いろいろな人が関わるわけですが、何のためにこの研究室があるのか、自分たちは何を目的とするのかをお互いにはっきりと共有して運営していくことが重要です。そのためには、お互いにうまくディスカッションしたり、それぞれがどういう人なのかをよく見ることが大事だということです。一つ、唯一絶対の解があるわけではありません。こうすれば研究室運営はうまくいくという話ではなく、それぞれ、どういうタイプの人なのか、どうやって全員が目的に向かっていくように研究室をうまく動かしていくのかを考えていくことが、非常に重要であるということを話されました。 そういったことを宮野先生からご紹介いただいた後、グループに参加した先生方で、それぞれ個別に抱えている問題などを話し合いました。特に話題になったのが、これは私が提案した質問なのですが、研究室の特に上の先生方、教授の先生方とどう付き合うか。それから、研究室に入ってくる学生さん。先ほどの最初の話にもありましたが、学生の質もいろいろ変わってきていて、意識が高い学生をどうするか、何もしない学生をどうするのかといったことも一つ一つ、人のタイプをよく見てコミュニケーションのスタイルを変えていくことで、結果的に大学の質を変えていけるのではないかということでした。研究室運営に対するいろいろなディスカッションができて、非常に良い時間を頂けたと思います。ありがとうございました。 |