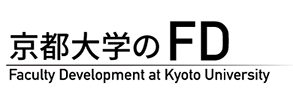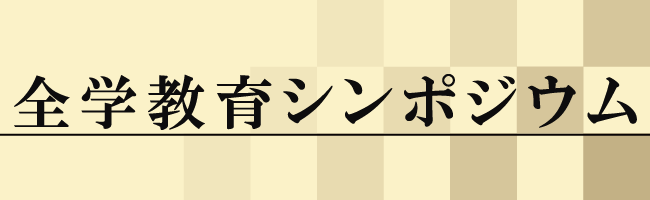- ホーム ->
- 主催 ->
- 新任教員教育セミナー(2013.9.10開催) ->
- グループ4「学生の思考力を鍛える」
新任教員教育セミナー(2013.9.10開催)
グループ4「学生の思考力を鍛える」
|
|
私たちのグループは、「学生の思考力を鍛える」というテーマで議論を行いました。講師の楠見先生によると、今回議論する思考力というのは学生の批判的思考であり、それをどのように鍛えるかということです。相手を批判するのではなく、自分を省みるような思考が、恐らく研究したいとか、社会のリーダーになっていく中で必要になっていくと思うので、私自身もそれが非常に重要だと思い、このテーマを選びました。 どうやったら思考力を鍛えられるかについては、まず、「授業への参加」という意味で、学生に分からないところを質問してもらうことに関して多くの議論が行われました。皆さんもよくご承知と思いますが、学生の質問が少ないことが問題になっています。その上でどのように学生の質問を引き出すか。楠見先生は、授業の最後に質問カードを学生にわたし、次の授業でその質問に対して答えるということを行っているそうです。あるいは、「全体で質問は?」と尋ねても学生からの発言が期待できないので、授業の最後に時間を取って、2~3人のグループで話し合いをさせ、盛り上がっているグループにその質問を受講者全体に紹介してもらうことによって、活発な話し合いが進められていく事例を教えていただきました。先ほどどこかのテーマで挙がりましたが、ネットを使った匿名だと意外と議論が加速することもあるので、そういった環境を活用するのもいいかという話もありました。 学生にいろいろディスカッションさせることによって、批判的な思考を鍛えることができるようですが、われわれのグループの議論では、理系の科目ではこれがなかなか難しいことが課題として挙げられました。理系は非常に知識が膨大ですから、知識を詰め込ませるための授業をしないといけない。例えば、医学部や薬学部などでは国家試験があるので、それに対応もしないといけない。理系では答えが一つの場合もあるので、なかなかディスカッションというわけにもいかず、どうしたらいいのか。理系では特に院生になってから、プレゼンをさせたり、研究費の申請書を書かせたりといったことで鍛えていくという側面があります。それでももちろん良いところもありますが。私の所属する工学系で感じていることとしては、批判的思考を教える前に修士で出て行ってしまうような問題がありますので、いかに早期に批判的思考を学生に教え、研究に興味を持ってもらえるのかを今後考えていかなければいけないと感じています。 議論の中で他に出てきた課題を紹介します。100人以上が受講するような大規模授業ではディスカッションはなかなか難しいのではないか、それに対してどうすればいいのかということや、一般教養では思考力をどのように教えたらいいのかという議論がありました。これらもなかなか難しい問題ですので、今後、持続的に考える必要があると感じました。私からは以上です。 |