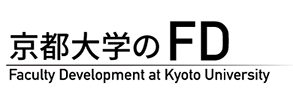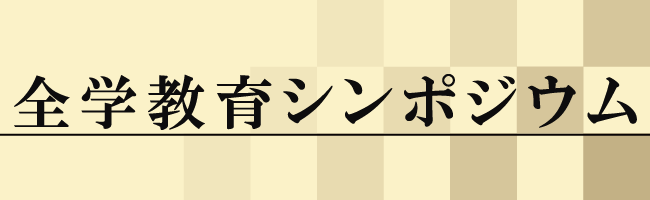- ホーム ->
- 主催 ->
- 新任教員教育セミナー(2013.9.10開催) ->
- グループ1「学生を授業に巻き込む―対話を根幹とした自学自習を本気で考えてみる―」
新任教員教育セミナー(2013.9.10開催)
グループ1「学生を授業に巻き込む―対話を根幹とした自学自習を本気で考えてみる―」
|
|
グループ1では、京大化研の平竹先生にポケットゼミのお話を伺いました。どのようなお話だったかを簡単に報告させていただきたいと思います。 私たちのグループの中で出てきた最初の問題点は、まず、学生とコミュニケーションを図る方法をどうすればいいかということでした。先生のお答えは、「王道はない。ガチンコ勝負である。人と人の交流だから、そこは距離を縮めていく」というものでした。確かにテクニックではなく、人間と人間の付き合いなのだと、あらためて目からうろこが落ちた次第です。 先生のご専門は有機化学で、先生のゼミには、ポケットゼミにしては多い約30人の学生さんが受講するのだそうですが、そこで実際に目の前で化学物質を見せて、それの粘性や特徴などについて、ものを見てもらって、触れてもらって、それにまつわる話をして、理解を深めるということをされているそうです。確かに実物を見せるのは一つの方法だと思います。一番感銘を受けたのは、毎回の授業のときに、必ず教科書の演習問題をやってもらって、そのレポート添削を非常に丁寧にされているということです。添削の内容を見ますと、good、excellentとか、やる気の起きるようなことも書き加えて、学生にフィードバックしておられることがわかりました。 最後に、教育と研究をどう両立するかという問題について議論になりました。平竹先生からは一つの案として、教育と研究の負担を教員によって変えるという提案があったのですが、それには対しては参加者から異論が出ました。やはり研究をしている人が教育をすべきである、教員の教育負担を減らすにはもっとTAを活用するというような方法もあるのではないか、といった意見が出されました。そこは多分、皆さん一番頭の痛いところだと思います。グループでも結論が出なかったのですが、引き続き考えていきたいと思いました。 |