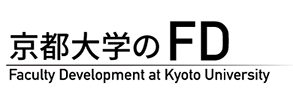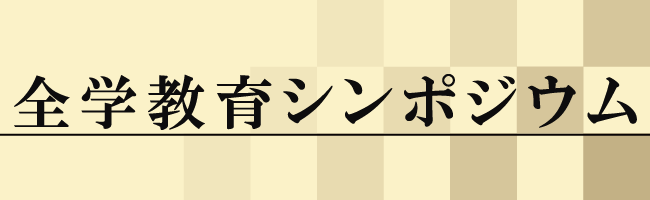- ホーム ->
- 主催 ->
- 新任教員教育セミナー(2011.9.1開催) ->
- グループ1「大講義をどう行うか?」
新任教員教育セミナー(2011.9.1開催)
グループ3「英語による授業をどう行うか?」
|
|
第3グループの農学研究科の吉永です。第3グループは「英語による授業をどう行うのか?」ということについて、ディスカッションを行いました。 今回G30という事例にどういう改善可能性があるかということを中心に話が進んでいたんですが、根本的な問題として、英語で貫くことが重要なのか、内容を相手に理解させることが優先なのか、ということがあり、これはなかなか解決しにくいのではないかということを感じました。まだまだこの問題点については、これといった正解はないということで、一人ひとりの先生が試行錯誤しながら授業をしていくしかないのではないか、というところに議論はまとまりました。以上です。 |
セミナーの映像は、京都大学OCWでご覧頂けます。
下記URLより、どうぞご覧ください。
https://ocw.kyoto-u.ac.jp/ja/center-for-the-promotion-of-excellence-in-higher-jp/02
***********************************************************************