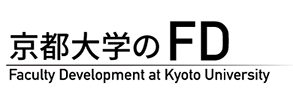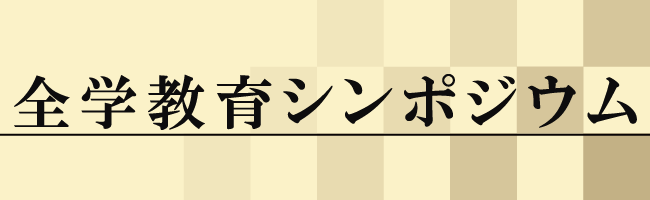|
京都大学における学生支援をテーマにした本セッションでは、最終的には23名の方が参加されました。修学、研究指導上で不適応を起こした学生に対して、教員としてどう向き合うかということについて、京大の状況や大学、大学院の時代の学生の不適応の様相を知り、学生と向き合うために必要な姿勢や「聴き方」の体験実習を行いました。
前半では、和田先生より冒頭60分ほどでミニ講義が行われました。講義の中では、まず「京都大学の学生支援体制について」のお話があり、近年では全学での支援に加えて、部局での支援として相談室や保健室が設営されていることが説明されました。また「数値で見る京都大学の全体像」として「カウンセリングルーム相談件数の経年推移」や「相談内容」、「留年」や「自殺」の状況が紹介されました。特に「自殺」の状況の比較として、内閣府発表の同年代の自殺死亡率も併せて紹介され、京都大学の数値が決して小さくないことがうかがわれました。さらに、「大学生活におけるつまづき」として、特に相談の多い内容についての事例が紹介されました。学生の相談内容には、学業や人間関係のみならず、生きがいやアイデンティティなど、さまざまな不適応の様相があることが示されました。本年度は特にコロナ禍にあって、人付き合いがなくなったことによる相談などもあったことも紹介されました。
そして後半では、ミニ講義の流れを受けて、学生のさまざまな悩みや困難を「知る」あるいは「気づく」ための話の「聴き方」として「傾聴」について説明されました。特に印象的だったのは、先生が相談学生から言われた「人に話を聴いてもらうというのは、何かアドバイスをもらうことより、そのまま受けとめてもらうことなんだと感じました」という言葉でした。引き続いて「傾聴」とはどのような聴き方なのかということについての基本的な方針や4つの基本メッセージ、「非指示的リード」「オープン・クエスチョン」、「非言語的メッセージの意識化」などの相談者から充分理解してもらうための聴き方について説明がありました。その後、Zoomのブレイクアウトルーム機能を利用し3~4人1組のグループに分かれ「傾聴」の体験実習を行いました。体験実習ではまず、「悩める学生役」としての役作りとして「悩みの内容」を考えていただきました。そしてグループでじゃいけんで順番を決めてもらい、自己紹介を行ってもらいました。その後「①悩める学生役」「②相談に乗る教員役」、「③、④見守り手+③タイムキーパー」の役割でロールプレイを実施してもらいました。ロールプレイの状況設定は「研究指導学生からZoomで相談を受ける」というものでした。残った時間では、グループでの振り返りを行っていただき、それぞれの役の中で感じたことなどを共有していただきました。役割を変えてもう1ターン行うことができ、全部で2ターン行うことができました。
最後にまとめとして、和田先生から「学生に対していつも「傾聴する」スタンスで関わることは現実的ではない」ということが語られました。教員の役割の中で学生を「指導する」ことは重要な仕事の一つで、ときには「アドバイス」したり、「指示・注意」、「叱咤激励」したりすることも必要な場面もあるだろうということです。これは、「傾聴」の適用についての重要なメッセージであると感じられました。
現在の学生の状況を知るだけでなく、相談の際にどのようなことが重要であるかといった実践的なことも学ぶことができ、大変有意義なセッションとなりました。
|