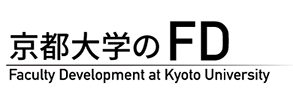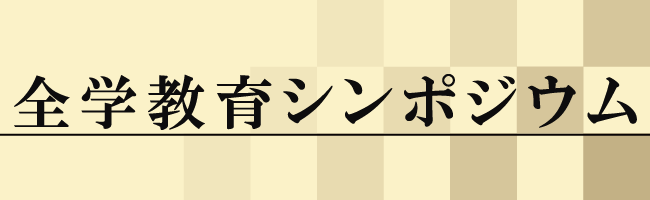- ホーム ->
- 主催 ->
- 新任教員教育セミナー(2015.9.25開催) ->
- テーマ1「『英語による授業』を担当することになったら」
新任教員教育セミナー(2015.9.25開催)
テーマ1「『英語による授業』を担当することになったら」
|
|
医学研究科メディカルイノベーションセンターの小柳と申します。私は英語でのレクチャーのやり方というところに行きました。流れとしては、喜多先生のレクチャーがあって、その後グループワークで、「皆さんで京大の1回生に対して英語で授業をします。留学生と日本人がミックスした授業です。この環境であなたは何を準備しますか。何が問題になると思いますか」というお題を与えられまして、30分弱の間ディスカッションをして発表するということをしました。やはり先生方は、自分が英語で発言する、レクチャーをするというところに悩みを抱えている方がかなり多いようなので、まず資料作りのところがかなり問題になるのではないのか。そして、学生から質問が出てきたときに自分が理解できなかったらどうしようとか、そういうことに悩みを抱えていらっしゃるようでした。 それに対する回答ですが、資料については、理系のところは比較的、もとから英語で作られているようなコンテンツになっていることも多いのですが、文系の方は時間がかかるだろうなと。これは時間をかけるしかないと思うのですけれども。あと、学生さんからの質問の話になったときに、そもそも授業のスタイルが日本語と英語ではだいぶ違いそうだなと。アメリカではグループワークが多いので、場合によっては日本人と留学生で1対1で対話的なディスカッションをしてもらう。そして、もし学生の質問が分からないときには、言い換えを求めるなどいろいろな方法があるのですが、それでも分からない場合というのは、実際、学生さんが中身を理解していないからちゃんと説明ができないというときもあるらしいので、英語が非常に堪能な、日英両方しゃべれる学生さんに頼るといったこともいいのではないか。その代わり、コンテンツを教えるのは自分ですよと。ただ英語の授業をしているのではないというところをこだわった方がいいと教えていただきました。 もう一つは、学生さんがちゃんと理解しているかというところが大事なので、これについては日本人と留学生の、しゃべるスピードはもちろん違うのですが、逆にそれを書き出すということになると、やはり京大に来る学生さんなので、かなり英語力はある。その時点で、知識量では京大の学生さんの方が圧倒的に強いことが多いので、その場合、そういうことを想定して、お題を与えたときにいきなり議論に入るのではなくて、いったん書いてもらう。その上でディスカッションをするという流れにすると、比較的よくまとまった議論ができる。そして、できるだけインタラクティブに、お互い協力し合うような雰囲気づくりが大切だということを教えていただきました。 |